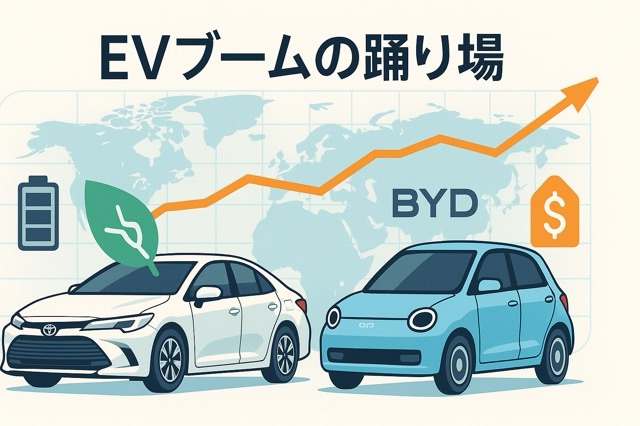――リード
EV販売は世界的に成長を続ける一方で、補助金縮小や価格競争の激化により“踊り場”に差し掛かっています。欧州では補助金打ち切りの影響で販売が足踏みし、消費者はハイブリッド(HV)や低価格EVへと目を向け始めました。トヨタはHV主体の「マルチパスウェイ」を再強化し、BYDは超低価格モデルと海外生産で攻勢を強めています。本稿では両社の次の一手と、それが日本株投資家に示すヒントを整理します。

【1 EV補助金縮小後の販売動向と戦略変更】
・欧州では2024年にEV販売が横ばいとなり、ドイツでは補助金終了後に24年のEV新車登録が前年比27%減少しました。HV登録はむしろ伸長し、電動化需要の“分岐”が鮮明です。
・こうした隙間を突く形で、BYDが25年4月に欧州BEV販売でテスラを初めて上回り、シェア拡大を加速させています。
・BYDは中国国内で税込7,800ドル相当の「Seagull」を投入し、価格競争を主導。海外でも20,000ユーロ以下の小型EVを投入予定で、低所得層・新興国の需要を取り込む構えです。
・一方トヨタは、HV比率が過去5年で9%→37%に急伸。米国や東南アジアなど充電インフラが十分でない地域を中心にHV需要を取り込み、EV生産計画(26年80万台)も当初計画比で約半減させてリスクを抑えました。
【2 バッテリー技術の進化と価格転嫁の課題】
・24年のリチウムイオン電池パック平均価格は前年比20%下落し115ドル/kWh、EV向けでは100ドル割れまで低下。コストプッシュ要因が緩和されつつあります。
・とりわけLFPセルは59ドル/kWhまで下がり、一部取引では50ドル近辺との報告もあり、BYDなど中国勢が価格優位を維持しています。
・もっとも素材価格の反発リスクや固体電池など次世代技術への研究費は重く、完成車メーカーが“値下げ競争で利幅を削る”構図は続く見通しです。
【3 日本株投資家としての注目ポイント】
〈HVバリューチェーン〉
・トヨタのHV増産で、インバータやモーターを供給するデンソー、アイシンの受注がひっ迫。部品不足による納期遅延が報じられる一方、長期的な設備投資と単価改善が追い風です。
〈電池素材・化学セクター〉
・LFP採用拡大でリン酸鉄系正極原料を手がける住友金属鉱山、正極・電解液用原料の三井金属や東ソー、セパレーターの旭化成などに再評価余地。パックあたりのコスト低減が進むほど、数量効果で収益拡大が期待できます。
・固体電池を含む次世代セルではトヨタ系のプライムプラネットエナジー&ソリューションズが24年から試験生産を開始。量産化が視野に入れば、関連の村田製作所(固体電解質)やAGC(固体電解質ガラス)がテーマ化しやすいでしょう。
〈市場全体への示唆〉
・欧州の補助金縮小と米国の関税強化(トヨタは25年度営業利益に最大8,000億円影響を試算)で、EVシフトは「地域ごとに速度が異なる局面」へ。マルチパワートレイン対応力とコスト競争力を両立できる企業が評価されやすい環境です。
――まとめ
EV一本足打法ではなく、HVや低価格EVを含む“多層戦略”が主流になることで、サプライチェーン全体に新たな投資機会が広がります。日本株では「HV深耕+次世代電池」で収益源を分散できる銘柄、中国勢の価格攻勢に対抗できる高付加価値部材メーカーが中期で注目どころです。補助金・関税・金利といった政策変動を日米欧中それぞれでモニターしながら、セクター横断でポートフォリオを再構築するタイミングと言えるでしょう。
#EV市場 #トヨタ戦略 #BYD #ハイブリッド #電池株