結果論に頼るほど、組織も個人も前進のエネルギーを失う。ここでは、両者に生じる具体的な弊害を掘り下げる。
(1)組織レベルの弊害
・会議が“振り返り”だけで終わり、次の一手が生まれない
多くの会議が「何がいけなかったか」という反省に偏り、結論が過去の検証で終わってしまう。
こうなると、新しい提案や行動計画は後回しになり、組織全体の実行サイクルが停滞する。
“次にどうするか”より“なぜ失敗したか”に時間を費やす――それは前進ではなく、停滞の確認作業だ。
・失敗事例ばかりが共有され、安全圏から動けなくなる
失敗を強調しすぎる文化は、チームの心理的安全性を奪う。
「またミスを指摘されるかもしれない」という恐れが先立ち、
小さく試すことさえためらうようになる。
結果として、革新的なアイデアや挑戦の芽が摘まれ、組織はじわじわと保守化していく。
(2)個人レベルの弊害
・チャレンジ意欲の低下と“失敗回避”の心理的コスト増大
「また失敗したら責められるかもしれない」――
その恐怖が行動を縛る。リスクを取ることへの心理的ハードルが高まり、
自ら成長の機会を遠ざけてしまう。
失敗を避けるために動かないことが、最大のリスクになっているのだ。
・自信喪失による決断力の減退
過去の失敗ばかりを思い返すうちに、「自分の判断は正しいのか」と疑うようになる。
小さな意思決定でも迷いが生じ、行動が鈍る。
こうして、積み重なる“ためらい”が次第に個人の機動力を奪っていく。
これらの弊害はいずれも、組織の革新力と個人の成長意欲を蝕み、
平凡な「後付けの安全策」に安住する温床となる。
次章では、この“結果論の罠”から抜け出し、未来を主体的に切り拓くための
具体的な思考法と実践ステップを紹介していく。
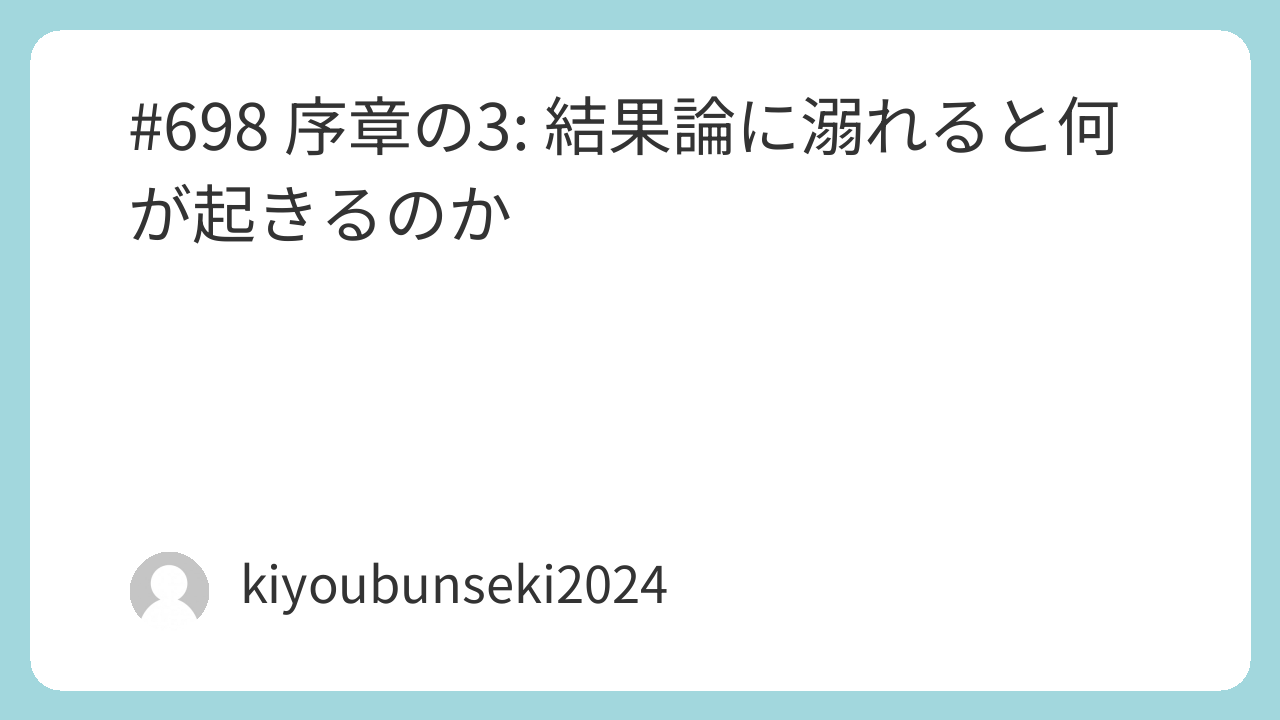
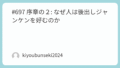

コメント