米中関係が再び緊張の度合いを強めている。中国政府が米国関連企業への輸出制限を強化する動きを見せたことで、世界の投資家は「リスク回避モード」に傾き始めた。東京市場も例外ではなく、為替・原材料・サプライチェーンといった複数の経路から、日経平均への逆風がじわりと強まっている。
14日の海外市場では、米国株が軟調に推移。S&P500は前日比で約0.8%下落し、安全資産とされる米国債や金に資金が流れた。背景には、米中対立の再燃に加え、欧州経済の減速懸念もある。これら複合リスクが、投資家の“リスク許容度”を下げている。
日本市場における影響経路は大きく三つだ。
第一に、輸出関連株の為替リスク。米中関係が悪化すれば、人民元が下落しやすくなり、円高圧力がかかる。円高はトヨタ(7203)やデンソー(6902)など輸出比率の高い企業の採算を直撃する。短期的には、為替ヘッジを行っていない中堅メーカーの利益修正リスクにもつながる。
第二に、素材・化学セクターの需要鈍化懸念。中国の景気刺激策が後退する兆しが出れば、鉄鋼・非鉄金属・化学など“景気敏感株”へのマイナスが避けられない。特に、JFEホールディングス(5411)や住友化学(4005)など、グローバル需要に依存する企業は注意が必要だ。足元の市況では原油や銅の先物価格がじり安基調にあり、素材株の調整リスクは高まっている。
第三に、サプライチェーン分断によるコスト上昇。米中間の制裁が拡大すれば、日本の電子部品・半導体企業にも波及する。特に、アップルやテスラなど米国企業への依存度が高い村田製作所(6981)やローム(6963)は、調達・販売の両面で影響を受けやすい。過去の米中摩擦期(2019年)にも同様の株価調整が見られた。
一方で、この“逆風相場”は見方を変えれば「ポートフォリオの見直しチャンス」でもある。相対的に強いのは、内需・防衛・エネルギーの3分野だ。
まず内需関連では、NTT(9432)やKDDI(9433)といった通信セクターが底堅い。為替の影響を受けにくく、安定した配当が投資家の逃避先となりやすい。
次に防衛関連では、川崎重工業(7012)やIHI(7013)など、政府防衛予算の拡大を背景に業績堅調が続く。地政学リスクが増す局面では相対的に買われやすい。
エネルギーでは、原油価格の変動が落ち着いてきた今、ENEOSホールディングス(5020)など資源株の下値余地は限定的だ。
個人投資家にとって重要なのは、「短期の材料」に振り回されず、構造的に強いセクターへ資金をシフトすることだ。米中摩擦は繰り返されるテーマであり、突発的なニュースでマーケットが乱高下するたびに、投資家心理が過剰に振れる。こうした時期こそ、定期積立や高配当株へのリバランスを検討する好機といえる。
今週の東京市場では、輸出株の戻りが鈍い一方で、防衛・通信セクターに資金が向かう流れが確認できる。来週以降は米企業決算の本格化も控えており、海外要因が引き続き相場を支配するだろう。
不安定な相場だからこそ、「何を買うか」より「何を避けるか」を意識したポートフォリオ構築が問われている。
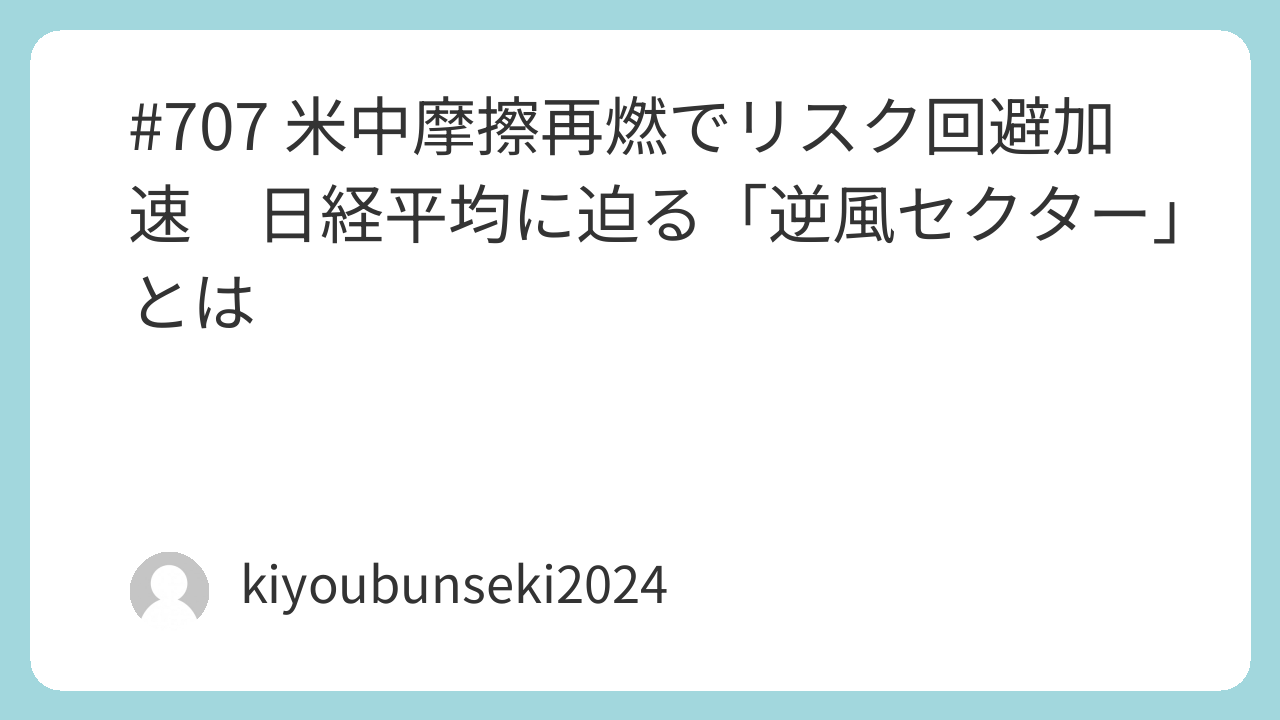
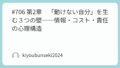
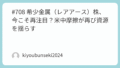
コメント