【イントロダクション(2025年10月13日 時点)】
6月に財務省が打ち出した「超長期(20・30・40年)減額/短中期・個人向け変動10年の増発」という方針は、その後も維持されています。9月下旬には年央見直しの具体案が示され、長期ゾーンの供給圧力を和らげつつ、1~5年の発行で埋める形が基本線です。一次ディーラーからも概ね支持が得られたと報じられています。(Reuters)
一方、政治は大きく動きました。10月4日の自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出。直後の10月10日、公明党が連立から離脱を表明し、与党体制は再編局面に入りました。市場は「財政・金融運営の方向性」を再評価しており、30年国債利回りは一時3.22%まで上昇する場面も見られました。(ウィキペディア)
【現状整理】
・財務省は年央の発行計画を見直し、20年・30年・40年の超長期は減額。一方で1~5年の短中期や流動性供給入札(オフ・ザ・ラン改善)に振り替える方針。発行の歪みを是正して流動性を回復させる狙いです。(Reuters)
・日銀は2025年度内のテーパリング方針は据え置きつつ、2026年度は「四半期あたり約2,000億円の減額」へ減速する計画を公表済み。金利や需給への副作用を抑えながら保有残高の縮小を進めるロードマップです。(Reuters)
・政治面では、自民党総裁に高市氏が就任予定。公明党の連立離脱で国会運営は流動化。10月10日前後には、政治不確実性を映して30年JGB利回りが3.2%台まで上昇するなど、超長期ゾーンが揺れました。(ウィキペディア)
【財政運営の狙い(視点は6月稿と同様に)】
市場機能の回復
・需給が歪んだ超長期ゾーンの発行を絞り、オークションの安定とタイト化した流動性の改善を優先。短中期と流動性供給入札の活用でカーブ全体の厚みを確保。(Reuters)
調達コストの抑制
・クーポンが嵩みやすい超長期から短中期へ一部シフトすることで、平均調達コストを抑える設計。6月時点の方針を踏襲。(Reuters)
個人マネーの動員
・個人向け変動10年(半年ごと見直し)への誘導は継続。家計の金利上昇局面での受け皿として評価余地。〔制度の基本枠組みは従来通り〕
【日銀との“合わせ技”のいま】
・2025年度末(~2026年3月)までは減額ペースを既定路線で継続し、2026年度は四半期2000億円減へ減速。供給減(財務省)と需要の急落回避(日銀)を組み合わせ、長期ゾーンの過度なボラティリティを抑える布陣は基本的に継続です。(Reuters)
【政治イベントの市場インパクト】
自民党総裁選の帰結
・高市氏は「成長重視・物価はコスト要因が中心」との見立てから、拙速な利上げには慎重姿勢。景気下支えの補正や減税(ガソリン税など)に前向きで、財政拡張バイアスが意識されています。これが一時的にJGB利回り上昇・円安方向の思惑を誘発。(Reuters)
公明党の連立離脱
・政治的安定度が低下し、予算・関連法案の通過難易度が上がるとの見方が増加。市場は「歳出規模・財源手当の不確実性」を織り込み、超長期中心にリスクプレミアムを上乗せ。10月10日前後に30年利回りが3.22%へ上振れ。(フィナンシャル・タイムズ)
高市氏の金融観
・「政府目標と整合的な日銀運営」を求める発言が注目を集め、日銀の独立性や利上げタイミングの思惑が交錯。結果として、超長期ゾーンのタームプレミアムが敏感化しています。(Reuters)
【イールドカーブの形状変化(アップデート版)】
・発行減の超長期(20~40年)は、本来フラット化要因ですが、足元は「政治・財政の不確実性プレミアム」が勝り、変動が大きい。イベントドリブンでスティープ化方向の揺り戻しが断続的に発生しやすい。(Reuters)
・5~10年帯は増発と日銀の買入減速見込みが重し。実需(生保・年金)の比重が高まるほど、10年近辺は相対的に重く、ベリーからウィング(超長期)へと歪みが波及しやすい局面。(Reuters)
【投資家が注目すべきポイント(2025年10月版)】
・生保・年金の運用シフト
政治イベントに左右される超長期のボラが残るため、政策の不確実性が落ち着くまでデュレーションの中立化(20年未満の厚め配分)を優先する向きが増加。イベント通過局面では30年・40年の逆張り需要が点発生。(Reuters)
・デュレーション管理(投信・ETF)
超長期ウェイトは機動的に。基準価額のボラ抑制を意識し、5~12年帯のコアを維持しつつ、ニュースフローで長端を増減する戦術が有効。日銀の買入減速と財務省の超長期減額の綱引きに合わせ、ベンチからの乖離を抑える運用が鍵。(Reuters)
・個人向け変動10年の再評価
家計には金利上昇耐性のある商品。下限付きで半年ごとに見直しがかかるため、定期預金代替としての位置づけは維持。政治・為替イベントによる短期的な市場ボラを直接取りに行かず、金利上昇局面の取りこぼしを避けたい層に親和的。
・為替とJGBの相関
成長重視の財政観・利上げ慎重論は、短期的に円安圧力と長端利回りのリスクプレミアム上振れを同時に招きやすい。補正規模と財源の示し方次第で相関が変化するため、ヘッジの同時設計(金利先物・通貨)を推奨。(Reuters)
【高市さんの考え(要点)】
・景気ファースト:需要不足を重視し、コストプッシュ型インフレ下での利上げに慎重。成長と賃上げを優先し、補正や減税で家計負担を下げる姿勢。(Reuters)
・金融政策との整合:政府の経済目標と整合的な形で日銀に最適手段を求めるとの立場。市場は「利上げ後ずれ・長端RP上振れ」を一時的に織り込む格好。(Reuters)
・外交・安全保障観は保守色が強く、公明離脱の背景にある政策距離(防衛・歴史認識など)も指摘されていますが、相場直結は主に財政・金融のメッセージです。(フィナンシャル・タイムズ)
【まとめ】
6月時点で示された「超長期減・短中期増」という発行の再設計は、10月時点でも継続し、テクニカルには長期ゾーン安定化に資する方向です。ただし、総裁選後の政局変動(公明離脱)と新政権の成長重視メッセージが、超長期のタームプレミアムを敏感化させ、30年利回りは一時3.2%台まで上振れ。今後は「補正規模・財源手当」「日銀テーパーマップ再確認」「他党との国会運営」の三点が金利の方向感を左右します。(Reuters)
投資家は、中期ゾーンをコアに据えつつ、政治イベントの前後で長端の増減を機動的に。個人は変動10年の再評価で、無理にイベント・リスクを取りに行かない選択肢も有効です。
(付記:SEO用の題名・ディスクリプション案)
題名案:政府、超長期国債の発行減額は継続へ――総裁選後の公明離脱と高市新体制が映す金利リスク(2025年10月13日)
説明文案:財務省の年央見直し(超長期減額・短中期増発)と日銀の買入減速計画を整理。自民党総裁選後の公明離脱、高市新総裁の政策スタンスがJGBカーブに与える影響を最新データで解説。(Reuters)
過去の類似記事
#691 政府、超長期国債の発行減額へ――金利上昇リスクに備える財政運営(2025年6月23日)
財務省が国債発行を異例の途中見直し|長期金利急騰と日銀QT鈍化の真意を読み解く | 中流ビジネスマンのBLOG
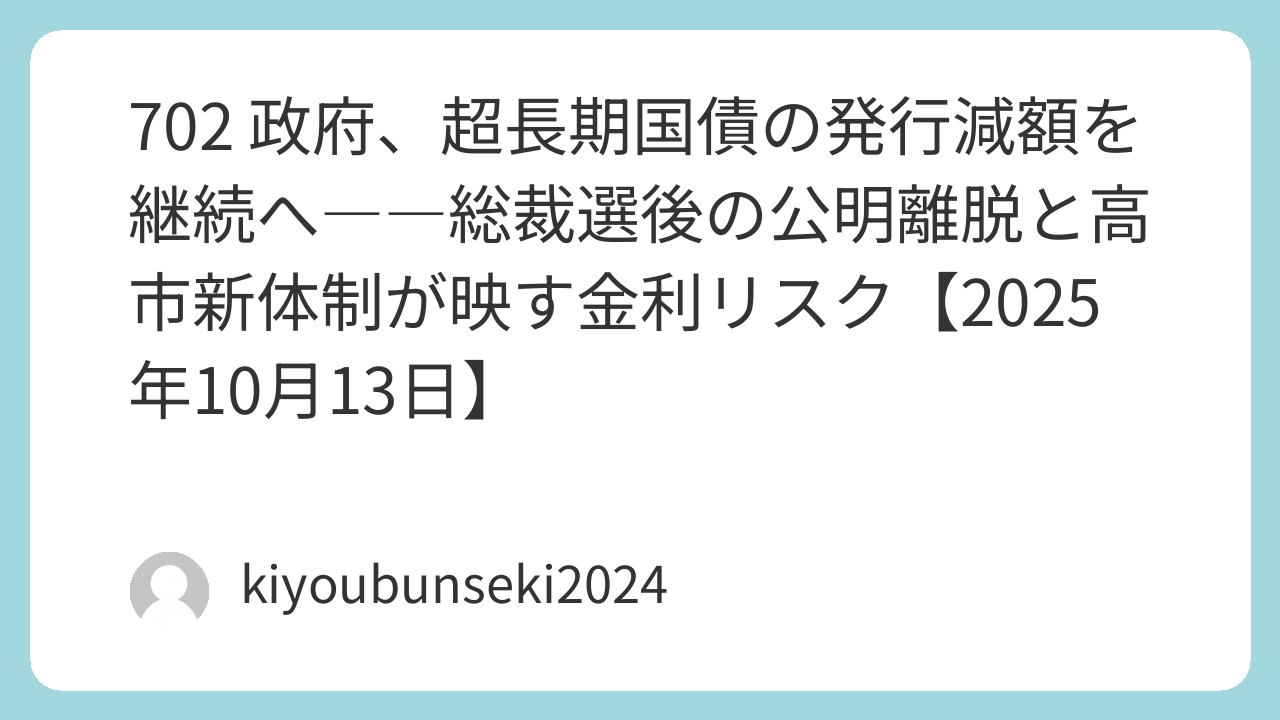
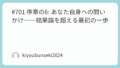
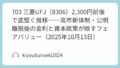
コメント